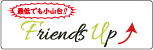ご覧いただきありがとうございます。
7月27日(土) に渋谷の大盛堂書店さんにて 作家であり教育者の喜多川泰先生の講演会に行ってきました。

教師限定企画 ということで、学校の先生や塾の先生しか参加できないものでした。
喜多川泰先生とのご縁は不思議なものでした。
妻がインスタで「運転者」という当時の喜多川先生の新刊を見つけてくれて私に紹介してくれたことから始まりました。
基本、小説は読まない私ですが、読んでみると独特の世界観とリズムが心地よく、内容も自分好みなものでした。
何より、登場人物のセリフが、直接的で力強く、自分に刺さりました。
そして、妻が喜多川先生の本にハマり、何冊か買ってきた中に私も一緒に面白いなと読んでいました。その中に大学受験のお話「なぜ人は勉強するのか」というテーマに挑んだ小説「手紙屋~蛍雪篇
これがめちゃくちゃ面白かった。
まさに納得!
比べて申し訳ないのですが、正直私以上に「なぜ人は勉強するのか」ということに関して表現が上手い!と思いました。
見事!さすがプロ!
こりゃかなわん。
という印象でした。
(その後、この本を何冊か買って必要な子に渡したりしました)
そして改めて、喜多川泰 という著者の名前を見ると
ん?みたことあるぞ。
となりました。
そうなんです。確かに見たことあるなと、ガサガサと昔にいただいた書類を掘り返すと・・・
ありました!喜多川泰!塾の先生で、以前ある出版社の担当から
「とてもうまくいっている塾があります。山根先生とタイプが似ていると思います。もし興味あるなら私が紹介するので見に行きませんか?」
とご紹介してくださった塾の塾長先生でした!
その時に、喜多川先生が新入会生用に書かかれた冊子があったのですが、そちらをもらっていたのです。
とても素晴らしい本だったのでとっておいたのです。
ビックリしました!
こんなところでご縁があるなんて!
フレンズアップ雑色時代、最後の方ですかね。もう塾も続けられず終わろうとするときのタイミングだったかもしれません。
まったくうまくいっていないときで、教材販売の担当者が声掛けをしてくださったのです。
ありがたいですね。
その時は、その塾まで距離もあるし、何より毎日が大変!と思っていた時期だったので、他塾様に勉強に行こうというそんな余裕すら持てなかったときでした。
そしてその後に雑色校は閉塾となったのです。
あれから、数年たって現在の蓮沼校にて再起して、頑張っているときにまた喜多川泰先生に出会ったのです。
そしたら、なんと塾で業務委託しているIT関連の担当者様も喜多川泰先生の大ファンで、講演会のスタッフ側としてお手伝いしたことがある方でした。
こんなに偶然が重なるのかと。塾に額に入れて飾ってある名言も、誰のものか知りませんでしたが(笑)、実は喜多川泰先生の言葉でした!
その言葉に感動した方が書にして、みんなに配っていたものをいただいて素晴らしいと私が感動して額にいれていたのです。
なんとなんとこんなご縁が。
そしてついに喜多川先生にお会いする日がきました。
7月27日です。
この企画も妻が見つけてきてくれました。
夏期講習と夏期講習の合間でしたのでタイミングよく参加できました。
大変申し訳ないことに、よく知らないまま講演会に参加するつもりで行きましたが、なんと講演会ではなく研修会でした。
喜多川先生が先生向けに新しく本を出版されて、その本を使っての研修会でした。
「サクラ咲け 優しき先生への道」


※サイン入り とてもうれしいです。(ヤッター!)
という本です。ティーチャーズバイブル ということでフレンズアップの授業マニュアルにはない視点で書かれていてとても参考になりました。
以下、研修会で学んだことです。
備忘録も兼ねて、学ばせていただいたことを書かせていただきます。
自分なんかが教師をやっていていいのかと思うことは誰でもある。
そういう人にこそ教師を続けてほしいと思う。
大事なことは、そんな時こそ、次にどこへ向かうかだということ。
生徒のために1ミリでもいい授業をしようとまた思えるのか。
ただそれを教えてくれる人がほとんどいない。
研修は楽しくないといけない。楽しまなきゃいけない。
喜多川先生は明日の授業研修は楽しみでしょうがない、と思えるもの、思ってもらえるものでないといけないと考えている。
人の研修を見るときは、1つ自分が学ぶものを探す。人を育てるときは自分のマネをさせるのではなく、その人の良さを引き出して自分を超えてもらうように接する。
僕のようになってほしいとは思わない。
自己研鑽を続けていって、その人しかたどり着けないところへ行ってほしい。
自己研鑽では自分で自分の授業をビデオで撮るといい。自分の感性でみてひっかかるところを直す。
他の人に見てもらうときは、一番うまいと思う先輩か信用できる人=同じ価値観で話せる人がいい。
みてもらったら自分から聞く。
自分が講師のときはアドバイスは聞かれなければ言わない。
授業では、塾などではあとから入ってくる人は、今入っている子たちの大事にしている文化を同じように大事にしてくれる人を入れる
例えば、宿題。宿題をやることが大事と思っているクラスには、宿題を同じようにやることが大事だと思っている人を入れる。
そうでないと、たった一人の人で全体がくずれる。
面白い授業というのは=笑える授業ではない。自分が面白いと思える授業。
これから生きるのに必要な力とは、健全な相互依存。もらった分、返す。
そうして世の中が回っていく。
先生は自分の言葉を大事にする。言葉を大事にするとは、口にしたことを自分から守ること。
生徒に言いっぱなしにならない。まず自分から。
挨拶が大事というなら、自分が挨拶を大事にする。
相手の目をみて話す。
それも結構な時間、相手の目をみる。
1対多数ではなく、1対1×人数 それは人間関係は基本1:1だから。
さらに、先生は人によって態度が変わってはいけないかというと喜多川先生の考えは違っていいと。
それは1:1ならそれぞれ関係性が異なるので、関係性が異なるなら対応も態度も変わってくるのが自然だからと。
あまり、全員に平等にということにとらわれずに、あくまでも目の前の人を大事にしていく中に、自然に接していく。
もちろん、横柄な態度は論外だし、ひいきするような態度もダメだが、一人ひとり丁寧に対応していく中で、関係性が異なるならそれぞれ自然な形で変わってきて当然だということでした。

※許可をもらって掲載させていただいております
以上となります。
感想は、私と考えがだいぶ似ているなと感じました。
また私が意識しているところでの共通点もたくさんありました。
似ているからこそ、教材の担当者もご紹介してくれようとしてくれたのかもしれません。
まずは挨拶を大事にするところもそうです。
大手時代「挨拶以上に大切なものはない!」と挨拶をないがしろにした中3クラスの生徒に向かって(主に男子ですが)一喝したことがありました。
卒業していくタイミングで何人かの男子たちがそのことを思い出として残っていると色紙に書いてくれました。
当時、とても大きな声で指導したので、受け止めてくれたこと感謝しました。
また数年前に出演させていただいただ「ありがとうTV」も思い出しました。
1:1 × 人数
はまさに同じことを意識しております。
ありがとう!TV
「子どもにとって一生に一度の授業」を大切に フレンズアップ代表 山根良友さん
※もう10年前になるのですね。山根、やせています(笑)
そして、相手の目をみて話をするところ、自分の言葉を大事にするところ、はそのまま私も同感でした。
私も、指示を出したら全員ができるまで次の行動を起こしません。全員ができるように場を整えていくのと、全員でチームで学習していくことを大切にしております。
文化を共有していくところなんかのお話も、まさしくそうだと感じ入りました。
以前の私はみんなを受け入れてやっていくのが技術だと思っていて、場を乱す子たちも巻き込んでやっていたところがありました。
そのため、どうしてもまじめでちゃんとやろうとしてくれている子たちが、その場では不利益を被ることがありました。時間を取られてしまったり、授業が先に進まなかったり、授業がギリギリになってしまったりです。
そのため、勉強が得意な子にはそこのフォローもしていきながら、さらに課題を出してあげるなどしていっていました。
これが理想でこれができる技術がみんなでやっていくことだと思っていました。
だから雑色時代では徐々に難しくなっていったのだと思います。
成績が伸びてもやめていく
もっとちゃんとやりたいと思う子もやめていく
最初の本人たちの動機づけもしっかりしなくてはいけなかったのだと気が付きました。
だからこそ今は、入会前にしっかりとルールを確認してからご入会とさせていただいております。
体験授業前に面談があって、なんのためにやりますか、という問いを答えてもらいます。
保護者様のご意向
本人の希望と困りごと
をお伺いします。
そして体験授業後にルールの確認します。
それでも希望があれば、次は入会「面接」となります。
私の方でも、しっかり判断させていただき、本人のやる気があるかどうか、本人がやりたいと思っているのかどうか、困っているのかどうか、保護者様のお困りごとは何かなどしっかり確認します。
その上で、ご本人様・保護者様・そして私の三者で同じ方向を向いているとなれば、入会となります。
フレンズアップでは学力による入塾基準などはありません。
志望校に偏差値30たりなかろうが、40足りなかろうが、本気で行きたいなら応援します。
だからこそ
3か月で偏差値30UPや
2年で偏差値40UP
苦手科目で学年1位
内申12UP
理科は山根の動画授業だけで毎年偏差値65以上を必ず輩出
全体の22%が平均して内申11UP
などなど実現できて来たのだと思います。
奇跡と呼ばれる結果を出せてきました。
これは三者でみんなで向かったからこそ達成できた偉業です。
本当に感謝しかありません。
今回こうして学ばさせていただき、改めて自身を振り返り、自分はできているとかできていないとかではなく、謙虚に学び続けなければとも思えました。
また新しい指標をいただけましたので、早速アンケートを作成して自分は本当にできているのか、いつものアンケートとはまた違う視点で生徒にチェックしてもらおうと思います。
ありがとうございました。
今回は長文となりました。
お読みいただきありがとうございました。
フレンズアップ
山根 良友
前回のブログはこちら
令和6年(2024年)度 フレンズアップの都立入試の結果と情報開示で分かったこと