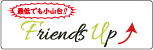ご覧いただきありがとうございます。
1学期期末テストが終わり、徐々に中学校でのテスト結果が返ってきているところもあります。
テストはまだこれからのところもありますし、明日から期末テストが始まる中学校もあります。
私学や高校生はこれからですね。
さてその中で、ある保護者様とやり取りをしていた際に、私が
「結果を褒めるとプレッシャーになってしまいますが・・・」
というお話をさせていただきました。
その際に、
「結果を褒めるとプレッシャーになるという観点はなかったです。この辺はどのように接するのがいいのですか。」
とご質問をいただきました。
ありがとうございます。
本当にこうして保護者様からご理解とご協力をいただけていること、ありがたく存じます。
大変光栄です。
とっても大事なご質問だなと思いましたので、こちらでしっかりとお答えしたいと思います。
私たちは、特にテストの点数が良かった時に、つい
(点数が良かったから)「よく頑張ったね」
と声をかけがちです。

実は、これは教育の観点では、あまり良くないことなんです。
なぜなら、そういわれたお子様は
いい点数を取ったから、褒められた。
いい点数を取ったから、認められた。
と思ってしまうからです。
これは同時に
いい点数を取らなければ、褒められない。
いい点数を取れなければ、認められない。
と考えてしまい、またそう感じてしまい
それが今後のプレッシャーやストレスとなります。
そして、そのプレッシャーやストレスが大きい場合
お子様がとってしまいがちな行動が
いい点数を取るために、どうすればいいのか と考え
そこには、極端な話、不正も含まれてしまうことがあります。
例えば、
虚偽の申告
や
不正行為
などです。
とにかく「いい点数を取ることを目的」としてしまいます。
ここが教育とズレてしまうところですね。
お子様への教育では
「いい点数を取ることを目的」とはしておりませんよね。
そうなんです。
結果を褒めるとこうして徐々にズレていってしまうこともあるのです。
確かに結果がよかったから褒めるのは、気持ちもわかりますし、絶対に間違いですとは言い切れませんが
なぜこうしたことになるかといえば
「結果は自分ではコントロールできないから」
です。
コントロールできないものを褒められても、コントロールできないために次はどうしたらいいのかわからなくなります。
そして、無理やりでもコントロールしようとすると、そこには無理が生じて 耐えられないストレスにつぶされてしまったり、自分を無理やり正当化して不正行為に走ってしまったりするわけです。
これは、実験があったそうで1990年代にコロンビア大学で「褒め方によって子どもたちの心や態度やどのように変化するのか」というものだったそうです。
衝撃的なことに、頭がいいねと褒められた子は、その後の自分の点数を発表するプレゼンではなんと40%の子が、とった点数より上の点数を報告したそうです。
40%
ってすごい数字ですよね。
これはその子たち一人ひとりの問題というより、やはり褒め方の問題が大きいと思える数字だと感じます。
ではどうすればいいのか。
それは「過程を褒める」ことです。
努力を褒める
やってきたことを褒める
そうすれば、その過程を褒められたので、もう一度その過程を繰り返そうとしてくれます。
また結果はあくまで結果でしかないので、そこでどんな結果であろうと
その子がダメだとか、いいとか そういう自己肯定感が低くなるようなことはないわけです。
私も常に、意識しているのは
テスト前に「今日までよくやりました。あとは何点でもいいです。今日までよくやってくれたこの過程が素晴らしかったと思います。」
と子どもたちには伝えます。
その上で、「でもいい点数を取るためにやってきたんだと思うから、そこは応援していますからね。明日頑張ってください。」
とお話します。
結果を褒めるとプレッシャーになる
というお話でした。
参考になりましたら幸いです。
ありがとうございました。
フレンズアップ
山根良友
第2回 山根の教育一人語り 「家族会議の重要性」
よかったらこちらもご覧ください。
【第2回】山根の教育一人語り ~家族会議の重要性~